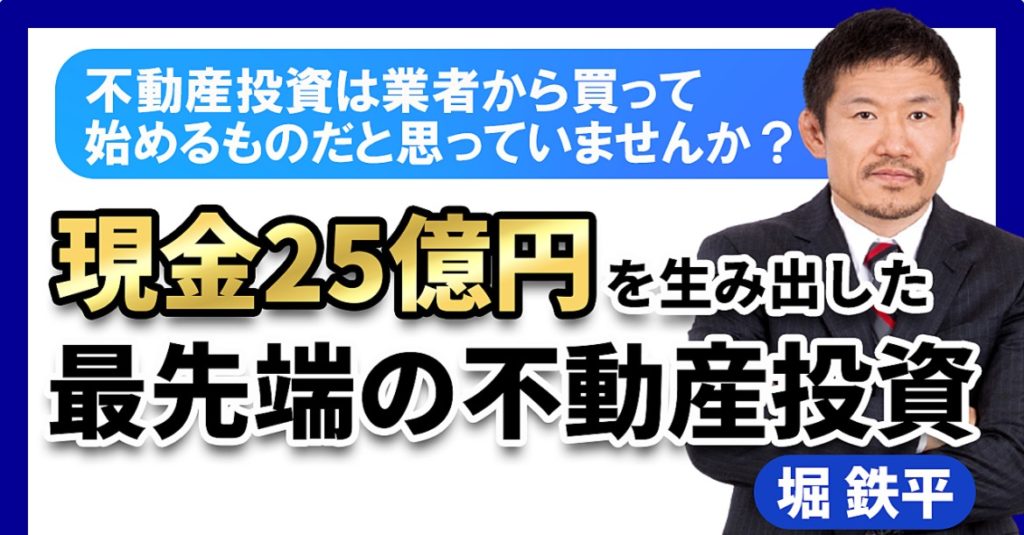<<第91回:競売物件は安いがリスクに注意する【不動産投資での競売物件の買い方】
記事のポイント
- 建物状況調査は建物の現状を把握するために行われる
- 建物の劣化・不具合等の状況をおおよそ3時間程度で検査する
宅建業法の改正による建物状況調査の取り扱い
2018年4月1日に宅建業法が改正され、既存住宅の取引において、媒介契約書に建物状況調査(インスペクション)の斡旋の有無が記載されるようになりました。必ず調査を実施するとは限りませんが、宅建業者はどのような調査なのかを把握し、顧客に説明する必要があります。
建物状況調査では、国土交通省の定める講習を修了した建築士によって、基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等を調査します。調査にかかる時間は建物の規模や状況等によって変わりますが、おおよそ3時間程度です。
あくまで、構造の安全性や日常生活に支障があると考えられる劣化事象等の有無について、目視等を中心とした非破壊による調査によって報告するものです。建物の瑕疵の有無を判定したり、瑕疵がないことを保証するものではありません。また、現行法規への違反の有無を判定するものでもありません。
媒介契約書
不動産の売却や購入の仲介または代理等を宅建業者に依頼する際の契約のこと。依頼できる宅建業者が一社のみの専属専任媒介と専任媒介、複数の宅建業者に依頼できる一般媒介にわかれており、専属専任媒介は自ら契約の相手方を探して契約すること(自己発見取)を禁止している。また、一般媒介には依頼している宅建業者を開示する必要のある明示型と開示する必要が無い非明示型がある
斡旋
仲介業者が間に入って双方をうまく取り持つこと
宅建業法改正の目的とは
法改正は、宅建業者が建物状況調査を実施する者の斡旋の可否を示すことにより、建物状況調査の認知度、実施率を向上させることが目的です。建物状況調査が広く実施されることにより、良質な既存住宅が流通しやすくなります。
検査内容と行われる状況
中古住宅は、新築とは違って維持管理や経年劣化の状況により建物ごとに品質等に差がありますが、その実態を購入希望者が見極めることは非常に困難です。
そこで、中古住宅の売買時やリフォーム時に現況を把握するために検査を行います。このときに、建物の劣化・不具合等の状況を検査することを、建物状況調査(インスペクション)と呼びます。調査が行われる状況は、主に次の3つのパターンに分けられます。
建物状況調査が行われる3つのパターン
- 中古住宅の売買時の建物検査や住宅取得後の維持管理の定期的な点検等
- 日常生活に生じている不具合を修繕する際に行われるもの(耐震診断等)
- リフォームの前後に住宅の劣化状況と性能を把握するために行われるもの
建物状況調査のメリット
建物状況調査を行うことで、調査時点における住宅の状況を把握したうえで売買等の取引を行うことができるため、取引後のトラブルの発生を抑制することができます。
建物状況調査のメリット・デメリット
| 買主のメリット |
|---|
|
| 買主のデメリット |
|
| 売主のメリット |
|---|
|
| 売主のデメリット |
|
まとめ
- 建物状況調査の斡旋の有無を記載するようになった
- 瑕疵や現行法規の違反の有無を判定するものではない
- 取引後のトラブルを抑制するメリットがある